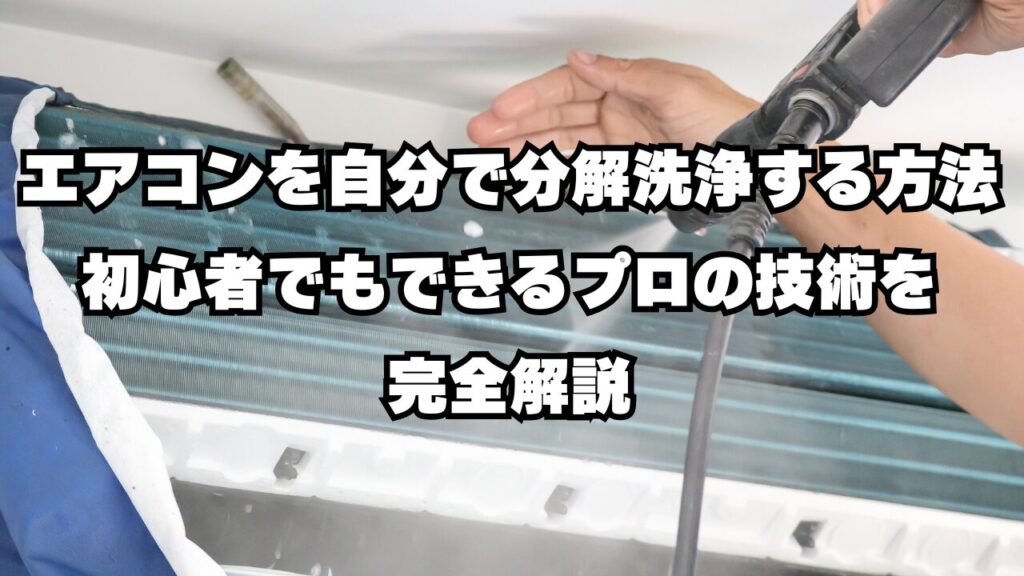エアコンを自分で分解洗浄する方法|初心者でもできるプロレベル手順を完全解説
エアコンの分解洗浄は本当に自分でできるのか?
夏場にエアコンをつけたとき、嫌な臭いがしたり、冷房の効きが悪いと感じたことはありませんか?フィルター掃除だけでは解決しない汚れやカビは、エアコン内部の熱交換器や送風ファンに蓄積しています。
プロに依頼すると1台あたり1万円前後の費用がかかるエアコンクリーニング。実は、基本的な知識と適切な道具があれば、家庭用の壁掛けエアコン(お掃除機能なしの標準モデル)であれば、自分で分解洗浄することも可能です。
もちろん、電気製品を扱う作業ですので慎重さは必要ですが、正しい手順を踏めば初心者の方でも安全に作業できるケースはあります。この記事では、エアコンクリーニング業者が一般的に行っている分解洗浄の手順やポイントを参考にしつつ、初心者の方にもわかりやすいように整理して解説していきます。
⚠️ 本記事を参考にする際の重要なご注意
本記事は、一般的な家庭用エアコンの分解洗浄方法を解説した情報提供用コンテンツです。実際の作業では、必ずお使いのエアコンの取扱説明書・メーカーの注意事項・使用する洗浄剤のラベル表示を優先してください。作業による故障・感電・水漏れ・怪我などのトラブルについて、当サイトでは一切の責任を負えません。少しでも不安がある場合や、構造が複雑な機種については、無理をせず専門業者への依頼をご検討ください。
💡 理解のヒント
エアコンの内部は、フィルターの奥に「熱交換器(アルミフィン)」と「送風ファン」という重要な部品があります。これらは市販の洗浄スプレーでは十分に洗えないことが多く、分解洗浄ではこれらの部品を直接洗浄することで、臭いの元となるカビや汚れを根本から除去しやすくなります。
送風口のカビ臭や効きの低下が気になるときは、プロの分解洗浄で熱交換器や送風ファンまで徹底清掃。 カジタク(KAJITAKU)なら料金・所要時間・オプションが明確です。複数台割引や防カビ仕上げの有無、予約可能日などは申込みページでご確認ください。 ※本リンクは広告を含みます。

自分で分解洗浄する前に知っておくべきこと
DIYでできる範囲とプロに依頼すべき範囲
まず理解しておきたいのは、すべてのエアコンが自分で分解洗浄できるわけではないということです。
✅ 自分でできる範囲
- お掃除機能なしの標準的な壁掛けエアコン
- 設置から10年以内の比較的新しい機種
- メーカーが一般的(パナソニック、ダイキン、三菱電機など)
- 本体カバーの取り外しが比較的容易なモデル
- 脚立などを使っても安全に届く設置場所
⚠️ プロに依頼すべき範囲
- お掃除機能付きエアコン(構造が複雑)
- 業務用エアコン(天井埋込型、床置き型など)
- 設置から15年以上経過した古い機種
- 特殊なメーカーや海外製品
- 高所で作業が危険な場所
- 電気系統や工具の扱いに不安がある場合
自分で洗浄するメリットとデメリット
DIYでの分解洗浄には、コスト面でのメリットがある一方、いくつかのリスクも存在します。
【メリット】
- 業者に依頼するより大幅にコストを削減できる(道具代を含めても初回2〜3万円程度、2回目以降は洗浄剤代などの消耗品のみ)
- 自分の都合の良い時間に作業できる
- エアコンの構造を理解でき、日常メンテナンスにも活かせる
- 複数台ある場合、繰り返し使える技術になる
【デメリット・リスク】
- 作業時間がかかる(初回は準備含めて3〜4時間程度を見込む)
- 部品破損や水漏れなどのリスクがある
- 養生や作業が不十分だと、基板故障の可能性がある
- 道具を一式揃える初期投資が必要
- 作業中の怪我や事故のリスクは自己責任
⚠️ 重要な注意事項
エアコンは電気製品です。作業前には必ずコンセントを抜き、ブレーカーも含めて電源を完全に切ってください。また、メーカー保証期間中の機種は、自己分解により保証が無効になる場合があります。作業は完全に自己責任となりますので、不安な場合は無理をせずプロに依頼することをおすすめします。
分解洗浄に必要な道具一式
エアコンの分解洗浄を行うには、専用の道具を揃える必要があります。すべて揃えると初期投資は2〜3万円程度かかりますが、一度揃えれば何度でも使用できます。
必須の道具リスト
1. 分解・組み立て用工具
- プラスドライバー(電動・手動):本体カバーやパーツを外すために必要。初心者は手動ドライバーかトルクの弱い電動ドリルがおすすめです。インパクトドライバーは力が強すぎてネジ山を潰す恐れがあるため、慣れるまで避けた方が無難です。
- マイナスドライバー:爪を外す際など、こじる作業に使用します。
2. 養生用品
- エアコン洗浄カバー(ホッパー):洗浄時の水飛びを防ぐ専用カバー。初心者には全体を覆うフルタイプが使いやすいです。
- マスキングテープ:壁を保護するために使用。粘着力が弱く、クロスを傷めにくいタイプを選びます。
- 養生テープ:基板保護や水漏れ防止に使用。
- マイクロファイバークロス(ウエス):1台あたり5枚程度あると安心。吸水性が高く、基板の養生や拭き上げに使用します。
- 不織布マスカー:基板を防水するために使用。
- 防水シート:床を保護するために必須です。
3. 洗浄用品
- 高圧洗浄機:家庭用エアコン洗浄に対応したタイプが理想です。数MPa程度の水圧があれば十分なケースが多いですが、実際の圧力設定は必ずお使いの機種の取扱説明書に従ってください。蓄圧式スプレーでも洗浄は可能ですが、高圧洗浄機の方が熱交換器の奥まで洗浄剤が届き、汚れ落ちが良くなる傾向があります。
- アルカリ性洗浄剤:油汚れやカビを分解します。多くの製品で10〜20倍希釈が目安とされていますが、必ずラベルに記載された希釈倍率・使用方法を優先してください。
- 弱酸性中和剤:アルカリ性洗浄剤を中和し、金属の腐食を防ぎます。こちらも一般に10〜20倍希釈が用いられることが多いですが、実際の倍率は製品表示を確認してください。
- バケツ(20〜25リットル程度):排水受けとして使用します。
4. その他
- ブロワー(送風機):洗浄後の水分を飛ばすために使用。
- ヘッドライト:暗い場所や奥の汚れを確認するために便利です。
- コーキングヘラ:養生時に隙間にウエスを押し込むために使用。
- ハサミ:マスカーやテープ類をカットするために使用。
- 振動吸収マット:高圧洗浄機の下に敷いて振動と騒音を軽減します。
💰 費用の目安
おおよその目安として、高圧洗浄機が1〜2万円前後、洗浄剤や養生用品で5,000円〜1万円程度、その他の道具で3,000円〜5,000円程度かかることが多いです。合計で2〜3万円の初期投資になりますが、プロに依頼すると1台1万円前後かかるケースが多いため、3台以上洗浄すれば元が取れる計算になります。
エアコン分解洗浄の基本手順
ここからは、実際の分解洗浄の手順を詳しく解説していきます。作業は大きく5つのステップに分かれます。
事前準備・動作確認
分解作業
養生作業
洗浄作業
組み立て・試運転
STEP 1:事前準備・動作確認
作業を始める前に、まずエアコンが正常に動作するか確認します。これは、万が一作業後に不具合が出た場合に、元々の故障なのか作業が原因なのかを判断するために重要です。
✓ 事前チェックリスト
- リモコンでエアコンの冷房・暖房が正常に作動するか確認
- ルーバー(風向き調整板)が正常に動くか確認
- 異音や異臭がないか確認
- 確認後、必ずコンセントを抜く(必須)
- コンセント部分を養生テープで保護し、誤って差し込まれないようにする
- 作業スペースを確保し、床に防水シートを敷く
STEP 2:分解作業
エアコンを分解していきます。機種によって細かな違いはありますが、基本的な流れは同じです。
【分解の順序】
①化粧パネル(前面カバー)を開ける
パネルを持ち上げて開き、左右のロックを外側に押して取り外します。フィルターも同時に取り外しておきましょう。
②ルーバー(風向き調整板)を外す
ルーバーは右側にモーターがついており、左側は差し込みだけになっています。取り外し方は2パターンあります:
- 方法1:モーター側をしっかり固定し、反対側をたわませて外す
- 方法2:真ん中のグレーの留め具を右側に押してスライドさせ、たわみを少なくしてから外す(破損リスクが低い方法)
③本体カバーを外す
本体カバーは通常、ネジ2本程度で固定されています。ネジを外した後、上部に3つのロックがあるため、本体を少し押してロックを外し、手前に引き抜きます。
④垂直板(左右の仕切り板)を外す
垂直板は洗浄の妨げになるため、できれば外した方が良いでしょう。爪で固定されているため、マイナスドライバーを奥側に入れて手前に引くと外れます。3つの爪があるため、それぞれ同じ要領で外していきます。
⑤サーミスター(温度センサー)を外す
黒い配線でつながっているサーミスターは、洗浄剤で腐食する恐れがあるため、必ず外します。留め具を外し、配線ごと取り外してください。※外したビスやパーツは、基板のそばに養生テープで貼り付けておくと、付け忘れを防げます。
⑥熱交換器上部のプラスチック板を外す
熱交換器の上にあるプラスチックの板は、洗浄時に水を弾いて飛び散らせる原因になります。裏面から外すと、熱交換器を傷つけずに取り外せます。
⚠️ 分解時の注意点
- ネジやパーツを紛失しないよう、小さな容器に入れて管理する
- 無理に力を入れると破損するため、構造をイメージしながら少しずつ動かす
- インパクトドライバーは慣れるまで使わない(ネジ山を潰す恐れ)
- 外した順番を写真やメモで記録しておくと、組み立て時に迷いにくい
STEP 3:養生作業
養生はエアコンクリーニングで最も重要な工程のひとつです。ここを手抜きすると、基板に水が入ってエアコンが故障する可能性があります。
【基板の養生(最重要)】
エアコンの右側には基板(電子回路)が集まっています。ここに水や洗浄剤が入ると、リモコンが効かなくなったり、温度センサーが故障したりするため、徹底的に養生します。
- マイクロファイバークロスで基板全体を覆う
- コーキングヘラを使い、ドレンパンのカバーとの隙間にクロスをしっかり押し込む
- 不織布マスカーで二重に覆う
- 養生テープでしっかり固定する
- 下部は少し開けておき、万が一水が入った場合の排水口として機能させる
【水漏れ防止の養生】
背面を洗浄する際、配管の隙間や壁との隙間から水が漏れる可能性があります。
- 配管と壁の隙間を養生テープで塞ぐ(「防波堤」を作るイメージ)
- エアコンを吊っている穴も養生テープで塞ぐ
- 配管周りにも養生テープで防水処理をする
【エアコン洗浄カバー(ホッパー)の取り付け】
初心者の方には、全体を覆うフルタイプのホッパーがおすすめです。支持金具を壁とエアコンの間に設置し、ホッパーを被せて固定します。ホッパーの下部にバケツを設置し、排水を受けられるようにします。
💡 養生の考え方
養生作業は「やりすぎ」ということはありません。プロでも毎回念入りに養生します。特に基板周りは、わずかな水分でも故障の原因になるため、「絶対に水が入らない」という意識で徹底的に養生してください。
STEP 4:洗浄作業
いよいよ洗浄作業に入ります。洗浄はおおまかに「アルカリ洗浄剤で汚れを浮かせる → 中和剤で中和する → 水ですすぐ」という流れで行います。
【アルカリ洗浄剤による洗浄】
アルカリ洗浄剤は、必ず製品ラベルの表示に従って希釈します。ここでは、説明しやすいように例として「20倍希釈」の場合を想定して解説しますが、実際にはお使いの洗浄剤に合わせて倍率を調整してください。
- 圧力は例として1.5〜1.8メガパスカル程度から始める(機種の許容圧力を超えないよう取扱説明書を確認)
- ノズルは最初「ストレート」で使用
- 熱交換器に対して直角に当てるように意識する
- 左右に振りながら、まんべんなく洗浄剤を行き渡らせる
- 表面だけでなく、可能な範囲で背面(裏側)もしっかり洗う
- 洗浄時間の目安:5リットル前後の洗浄液を使い切るイメージで、汚れの状況に応じて調整
【送風ファンの洗浄】
送風ファンも汚れやカビが付きやすい部分です。
- ファンを手で押さえながら、ゆっくり回転させる
- ノズルをファンの内部に差し込んで洗浄剤を噴射
- ファンが高速で逆回転しないように注意(モーター故障の原因)
【ドレンパンの洗浄】
ドレンパン(結露水を受ける受け皿)の内部や裏面も、カビが発生しやすい場所です。垂直板を外しているため、奥まで手を入れて洗浄できます。
【中和剤による中和】
アルカリ洗浄剤を残したままにすると、金属が腐食したり、プラスチック部品が劣化したりする恐れがあります。必ず中和剤で中和します。ここでも倍率は製品ラベルに従い、説明の便宜上「20倍希釈」を例にします。
- 弱酸性中和剤を表示どおりに希釈する(例:20倍希釈など)
- 圧力は2.0〜3.5メガパスカル程度を上限の目安とし、アルミフィンを痛めないよう様子を見ながら調整
- アルカリ洗浄剤を使用した全ての箇所に噴射
- 洗浄時間の目安:5リットル前後の中和液を使い切る程度
【水によるすすぎ】
最後に、除菌水や清水で全体をすすぎます。
- アルカリ成分が残らないよう、念入りにすすぐ
- すすぎ時間の目安:10リットル程度の水を使用
- 洗浄剤が弾いて飛び散っている可能性のある箇所(鉄板、側面など)も忘れずに洗う
【水分の除去】
洗浄後は、しっかりと水分を取り除きます。
- ブロワー(送風機)で熱交換器の水分を飛ばす(弱めの風量で、同じ場所に当て続けない)
- 送風ファンはブロワーで回すのではなく、手で回しながらマイクロファイバークロスで拭く(モーター保護のため)
- ドレンパンの内部も、奥までクロスを差し込んで拭き上げる
- 垂直板を外しているため、奥まで手を入れて拭ける
⚠️ 洗浄時の注意点
- 高圧洗浄機を使用する際は、必ず振動吸収マットを敷き、近隣への騒音にも配慮する
- 熱交換器のアルミフィンは非常に柔らかいため、近距離から強く当てすぎると曲がる恐れがある
- 送風ファンを高速で逆回転させると、モーターが故障する可能性がある
- 中和を怠ると、数ヶ月後に腐食や故障の原因になる場合がある
- 水分が残ったまま運転すると、水しぶきが飛び散ったり異音の原因になることがある
STEP 5:組み立て・試運転
洗浄が終わったら、養生を外して元の状態に組み立てます。
【養生の取り外し】
- ホッパーを外す前に、ブロワーでしっかり水分を飛ばしておく(飛び散り防止)
- 養生テープやマスキングテープを丁寧に剥がす(壁紙を傷めないようゆっくり)
【組み立ての順序】
- サーミスター(温度センサー)を元の位置に戻し、ビスで固定
- 熱交換器上部のプラスチック板を取り付け
- 垂直板を奥から差し込み、手前の爪をパチパチと音がするまで押し込む
- 本体カバーを取り付け、上部の3箇所の爪をしっかり押し込む
- ビス2本で本体カバーを固定(締めすぎないように注意)
- ルーバーを取り付け(モーター側をしっかり固定してから差し込む)
- フィルターを取り付け
- 化粧パネルを取り付け
【試運転】
組み立てが完了したら、必ず試運転を行います。
- コンセントを差し込む
- リモコンで電源を入れる
- 「送風運転」で最低1時間運転(冷房や暖房ではなく、送風で内部を乾燥させるイメージ)
- リモコンが正常に動作するか確認
- 異音や異臭がないか確認
- 室内側・室外側ともに水漏れがないか確認
💡 なぜ送風運転なのか?
洗浄後に防カビ・抗菌剤をコーティングする場合、送風運転の方がコーティングの定着が良いとされています。また、内部をしっかり乾燥させることで、カビの再発生を防ぐ効果も期待できます。
失敗しないための実践アドバイス
初心者が特に注意すべきポイント
1. 養生は「やりすぎ」くらいで丁度良い
エアコンクリーニングの事故で最も多いのは、基板への水の侵入による故障です。「リモコンが効かなくなった」「温度センサーが故障した」といったトラブルは、ほとんどが養生不足に起因します。基板周りの養生は、初心者の方こそ念入りに行ってください。
2. インパクトドライバーは慣れてから
インパクトドライバーは作業効率が良い反面、力が強すぎてネジ山を潰してしまうことがあります。最初は手動ドライバーか、トルク調整のできる電動ドライバーで作業し、慣れてからインパクトを使用しましょう。
3. 中和を絶対に忘れない
アルカリ洗浄剤は強力ですが、残留すると金属を腐食させる可能性があります。数ヶ月後にエアコンから白い粉が出てきたり、配線が腐食したりするトラブルは、中和不足が原因となることがあります。中和剤での洗浄は必ず行い、最後に水ですすぐことを忘れないでください。
4. 送風ファンの逆回転に注意
送風ファンに高圧洗浄機やブロワーの風を当てると、ファンが高速で逆回転します。これはモーターに大きな負担をかけるため、必ず手で押さえながら作業し、必要以上に回転させないよう注意してください。
5. パーツの付け忘れ防止策
サーミスターなどの小さなパーツは、外した後に付け忘れることがあります。外したビスやパーツは、基板のそばに養生テープで貼り付けておくと、組み立て時に気づきやすくなります。
作業時間の目安
- 初回:3〜4時間(道具の準備、分解・組み立ての確認含む)
- 2回目以降:2〜3時間(慣れてくると短縮できることが多い)
- 試運転:最低1時間(送風運転で内部を乾燥)
トラブルシューティング
Q. 試運転後、リモコンが効かなくなった
A. リモコン受信部(基板周辺)に水が入った可能性があります。もう一度本体カバーを外し、基板周辺の水分をブロワーで飛ばしてください。ホコリが原因の場合もあるため、基板には直接触れず、優しくホコリを除去します。
Q. 組み立て後、水漏れが発生した
A. ドレンパンの組み付けが不完全だったり、ドレンホースが詰まっている可能性があります。ドレンパンの位置を確認し、ドレンホース内に詰まりがないかチェックしてください。
Q. 洗浄後も臭いが残っている
A. 送風ファンやドレンパンの裏側など、洗浄が不十分だった可能性があります。これらの部分は特にカビが発生しやすいため、次回は重点的に洗浄してください。また、日常的な送風運転で内部を乾燥させることも大切です。
Q. 冷房の効きが以前より悪くなった
A. 熱交換器のアルミフィンが曲がってしまった可能性があります。アルミフィンは非常に柔らかいため、高圧洗浄機の圧力や距離を調整し、直角に当てるよう注意してください。フィンが目立って変形している場合は、プロへの相談も検討しましょう。
プロに依頼した方が良いケース
以下のような場合は、無理に自分で作業せず、プロに依頼することをおすすめします。
- お掃除機能付きエアコン(構造が複雑で、分解に専門知識が必要)
- 設置から15年以上経過した古い機種(部品が劣化しており、破損リスクが高い)
- 高所に設置されており、脚立を使っても不安定な場合
- 初めての作業で不安が大きい場合
- メーカー保証期間中の機種(自己分解で保証が無効になる場合がある)
- 水や電気の扱いに不安がある場合や、持病などでバランスを崩しやすい方
定期的なメンテナンスでエアコンを長持ちさせる
分解洗浄は年に1回程度で十分なことが多いですが、日常的なメンテナンスを行うことで、エアコンの寿命を延ばし、次回の分解洗浄を楽にすることができます。
日常的にできるメンテナンス
- フィルター掃除:2週間に1回程度、フィルターを外して掃除機でホコリを吸い取る。汚れがひどい場合は水洗いしてしっかり乾かしてから戻す。
- 吹き出し口の拭き掃除:月に1回程度、吹き出し口やルーバーを固く絞ったタオルで拭く。
- 室外機周辺の清掃:室外機の周りに物を置かず、風通しを良くする。
- ドレンホースの確認:ドレンホースが詰まっていないか、虫が入り込んでいないか定期的に確認。
- 使用後の送風運転:冷房使用後は、30分〜1時間程度送風運転をして内部を乾燥させるとカビ予防になります。
分解洗浄の頻度
- 一般家庭:年に1回(使用頻度が高い場合や、ペットがいる家庭・喫煙環境では年に2回)
- 飲食店・事業所:年に2〜3回(油汚れや粉塵が多いため、頻度を高める)
- 賃貸物件:入居者が変わるタイミングで実施
まとめ:エアコンの分解洗浄は準備と知識があれば自分でも挑戦できる
エアコンの分解洗浄は、一見難しそうに見えますが、基本的な手順を守り、適切な道具を揃えれば、初心者の方でも十分に挑戦できる作業です。
特に重要なポイントは以下の3つです:
- 養生を徹底する:基板への水の侵入を防ぐため、養生は念入りに行う
- 中和を忘れない:アルカリ洗浄剤は必ず中和し、金属の腐食を防ぐ
- 無理をしない:不安がある場合や複雑な機種は、プロに依頼する
初期投資として2〜3万円程度かかりますが、一度道具を揃えれば何度でも使用できます。プロに依頼すると1台1万円前後かかるケースが多いため、複数台のエアコンがあるご家庭や、毎年クリーニングしたい方にとっては、十分に元が取れる投資といえるでしょう。
ただし、分解洗浄の作業は完全に自己責任となります。不安な場合や、お掃除機能付きエアコンなどの複雑な機種については、無理をせずプロに依頼することをおすすめします。
定期的なメンテナンスと適切なクリーニングで、エアコンを長持ちさせ、快適な空調環境を保ちましょう。
自分でやるか、プロに任せるか迷っている方へ
「道具を揃えてDIYに挑戦するか、それともプロに任せるか…」と迷っている方は、一度プロの料金やサービス内容も比較してみると判断しやすくなります。エアコンの状態や設置環境によっては、最初の1回だけプロに依頼して様子を見る、という選び方もあります。
※サービス内容・料金・対応エリアなどは、必ず各サービスの公式サイトで最新情報をご確認ください。
参考・出典
本記事は、一般的な家庭用エアコンの構造と、エアコンクリーニング業者が行う代表的な分解洗浄手順を参考に再構成した解説記事です。作業内容の参考として、くらしのマーケット大学による家庭用エアコン分解洗浄の解説動画などを参照しています。動画の内容をそのまま文字起こししたものではなく、一般的な注意点や手順を整理した情報提供用コンテンツとして作成しています。